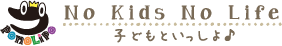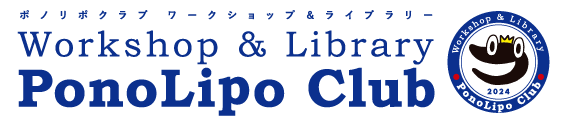PonoLipo Clubも開校して1年半、生徒さん各自それぞれ、その子なりの成果を上げています。PonoLipo Clubでは、「思考する空間を広く深く形成していく」ということが、教科に関わらず最重要と考えています。
PonoLipo Clubが、「本を読むこと」を積極的に取り入れているのは、本の中の世界を想像しながら読んだり、図鑑や事典で調べ物をして考えたりしていくことが、特に将来高等教育に進むためのアカデミックな思考空間形成に最良最速最善の道と考えているからです。
物語や図鑑・事典などを通して、私たちは世界中を旅することができます。もっと言えば他の星や宇宙の果てまで想像して、自分自身の意識を広げ飛ばすことができるのです。何万年、何千年、何百年昔の過去から未来まで、時空を超えて旅する事も可能です。この外側に大きく思考を広げ深く思索していくことが、強力なメタ認知力に繋がります。大学以上の高等教育を目指すのであれば、この思考空間の広がりを育んでいく必要があります。
また、読書は、著作者や作家といった識者との深い対話体験でもあります。いろいろな分野のさまざまな著作を読んでいくことによって、「書いてあることを鵜呑みにして受け売りする」というようなチープな洗脳を免れ、「自分は、どう考えるか?」「この部分は共感するが、ここには違和感を感じる」といったクリティカル・シンキング(批判的思考)の作法が自然と生まれ、自分とは何をどう感じ考える存在なのかという「自分自身のアイデンティティ」が明確になっていきます。自分自身の輪郭が、偉大な先人達との対話により明確になり、識者と共感していくプロセスで「自分は間違っていない、大きな歴史の流れの中に身を置いている存在」だという、揺るぎない自信が生まれていきます。
思考が外へ向かえばメタ認知に、内側へ向かえばアイデンティティの確立と自己肯定感に向かっていくわけです。この両方の思考を支える情報や知識、対話の体験が、潤沢で良質なものかどうかで、思考空間の深さ広さも規定されていくと考えられます。
このように、「思考空間を広く深く形成していく」のに、読書は、最も手頃で身近で最善の方法なのです。PonoLipo Clubのライブラリーでは、幼少期から思春期前期くらいまでを対象とした幅広いジャンルの良書を厳選して揃えています。良質な読書体験が、高等教育を目指す子どもの思考空間を広げ深めていくためには必要と考えているためです。
本を読まなくても、日常家族や友人との間で活発な会話のキャッチボールがされていて、一対一でじっくり話し込む対話の場面があれば、大人になって生きていくために必要な思考空間は、健全に育まれていきますので、読書が苦手な内は、その子の話をじっくり聴いて対話する時間と家族でワイワイ会話する場面を増やすように心掛けて下さい。絵本の読み聞かせは、一対一の対話のきっかけを作る道具として便利です。絵本の内容から離れて脱線してしまって構いません。子どもが想起して話しだすことから、丁寧に対話していって下さい。大人が、どう感じるか考えるかも、「私は、こう考える」という一人称で語って上げて下さい。「普通は」とか「男(女)は」というようなステレオタイプの大きな主語で話をするのは避けて、一対一で子どもと真摯に向き合って話をする事が大切です。また、ボードゲームやカードゲームは、家族でワイワイ会話する機会作りにとても有効です。リラックスしてたわいのない会話を日常重ねていくということは、家族や親しい友人としかできない大切なコミュニケーションです。その積み重ねから、お互いへの理解と尊重が生まれ、一対一の対話の場面をより親密で大切な時間にしていくのです。親子間の信頼関係は、一朝一夕で得られるものではなく、日常の積み重ねの中でしか育まれていきません。親が先ず楽しいと思える形で「親子で一緒に遊ぶ」事が、親にとっても子どもにとっても、自然で楽しい交流場面を日常に生んでいきます。
小学校中学年の時点で、本を読むことが、明確に苦手なお子さまには、音楽やスポーツ、アート、クラフト、ダンス、芝居などのアクティブな活動を通して、いろいろな人と交流し世界を広げ、活動していく中で自分と向き合い試行錯誤していく機会を積極的に設けていくと良いと思います。こうした人的交流と動的な活動によっても、充分思考空間を広げ深めていくことが可能です。思考空間が大きく広がり深まっていけば、自分自身の意志によって、その後圧倒的に学究の道に入っていくケースも、ままありますので、先ずは、その子に合った形で、無理なく思考空間を育んでいくことにフォーカスし、それぞれの子どもの成長と志向性に合わせて、周囲の大人も一緒にその子らしい人生探究の道筋を探していけば良いのではと思います。